
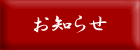 |
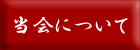 |
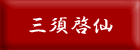 |
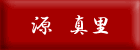 |
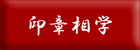 |
 |
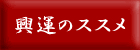 |
 |
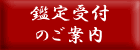 |
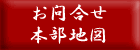 |

第19回 本当に印は無駄の権化なの? 前編
![]()
日本は、ハンコ社会である。何をするにもハンコが必要で、役所とお金がからむとその傾向は特に顕著になる。ここのところ印章無用論の火の手が社会のあちこちから上がっている。そんな中で、私は印という視座から社会の無駄を見直すことを試みてみた。
![]()
一昔前、政府発表をうけて、新聞紙上には"印鑑なしで手続きOK"の文字が躍った。役所への申請書類などに押印が必要だった手続きのうち、パスポートの発給、住民票の写しの交付、車検など6367件の手続きについて押印が無くても差し支えないとする行政手続きに簡素化をまとめたということだ。今回の手続きの簡素化では、"書類に押印する"という行為が簡素化の対象になった。まるで押印こそが無駄の権化とでもいわんばかりの扱いである。
![]()
昨今、印鑑と押印という行為が、まるで社会の進歩と合理化の天敵であるかのように疎まれているのである。こうなった原因の一つに、社会における印章使用法の乱れきった実情がある。
![]()
今、印章業界では、ハンコ社会が一挙に押印廃止の方向へ動き出すのではないか!ということで驚天動地の大騒ぎとなっているが、印の本質を忘れ、大量の三文判(三文の値打ちも無い印)を垂れ流して、印のスタンプ化、文房具化に拍車をかけ、印を本来の在るべき姿から遠ざけてきた業界一部の責任は軽くは無く、一概に同情はできない。ハンコ社会と呼ばれる現代は、印の本来有るべき姿、印章道?の立場からみれば、印鑑の乱用と混乱の時代と呼ぶに相応しい。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會