
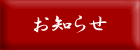 |
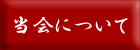 |
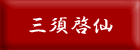 |
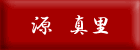 |
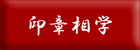 |
 |
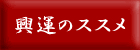 |
 |
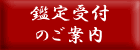 |
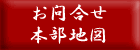 |

第21回 九星の由来から 前編
![]()
東洋占術の基本データとなる暦(カレンダーではない)は、十干、十二支、九星という三つの要素の組み合わせから成り立っている。十干は天の気を司り、十二支は地の気を司る。そして、乾坤感応。天と地の気が交錯し、交流するところに人は存在し、天と地の間で生きる人の気を九星が司る。 私は暦を見るとき、人間界の諸事は自然界の中で営まれているという当たり前のことを改めて思い知る。
![]()
何かが生じるには、それを生じるに至る、曰く所以というのが必ず存在するものだ。それはネーミングにおいて特に顕著である。 一白水星、二黒土星、三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星の九種類から成る九星は、その九タイプのエレメントに対して、一から九までの数と色と五行の組み合わせでネーミングされている。 この九つの星にそれぞれの色が配当された理由には諸説があるが、その中で私が一番納得できたのは、それは季節の推移に伴って移り変わる大自然の色の変化の様子を写しとったものだという説であった。中でも印象に残ったのが、六白金星、一白水星、八白土星の三つの星の名前に白が配当された理由である。
![]()
結果的には、これらの星の定位としている場所に、その色を配当された秘密があった。 少々込み入ったことになるのだが、話はまず、六白金星、一白水星、八白土星の三つの星が、それぞれ後天定位盤の西北、北、東北のエリアを定位としているというところからスタートする。(もちろん、これらの星がその場所を定位としているのにも深い理があるのだが、それはひとまず置いておくとして…)次は、これらの星の定位となっている方位を十二支であらわす。すると、西北は戌亥、北は子、東北は丑寅の方位ということになる。さらに、この十二支を月を示す代名詞としての意味に置き換える。そうするとそれは(旧暦の)戌…十月、亥…十一月、子…十二月、丑…一月、寅…二月となり、つまり晩秋から早春に至る期間を表すことになる。実はここに、六白、一白、八白の三つの星に白の色が冠せられた理由が潜んでいたのだ。それは、九星のネーミングがなされた頃、この思想を生み出した風土は、この時期に(雪で覆われた)大地が白く見えたからなのだという。
![]()
もし、九星占術が、冬の大地が雪で覆われることの無い常夏の風土の中で生まれていたとしたら、六白にも一白にも八白にも白という色が冠せられることは無かったかもしれない。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會