
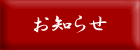 |
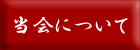 |
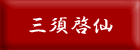 |
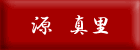 |
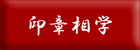 |
 |
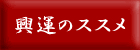 |
 |
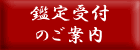 |
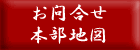 |

第22回 九星の由来から 後編
![]()
私は九星のネーミングの由来としてのこの説を「ああ、なるほどね」と何の抵抗もなく受け入れることができた。 一面の白…。すべてが真っ白で覆い尽くされた世界…。雪国に育った私は、苦も無くその様子を思い浮かべることができたからだ。冬の朝、窓の外にその光景が広がっている事に私は何の不思議も感じはしなかった。私にとって、冬は雪が降るものというのが当然の認識だったのだ。
![]()
私は、何ごとに関しても、ものごとを感性で「ああそうね」とスンナリ受け入れることができるのは、それを受け入れやすい文化的土壌をその人が持っているからなのだと思う。 もし、私が雪国ではなく、常夏の国で生まれ育っていれば、ああはスンナリと納得できなかったに違いない。
![]()
私は、ある意味で、人のつきあいというのは文化の交流であると思う。
![]()
私たちが、それぞれの人生の中でつきあう人々の中には、うちとけやすい人とそうでない人がいる。私は、これは、それぞれの人が有する文化の質の違いが生み出す現象なのだと思っている。 相互の文化が近いかそうでないかの違いから生じる差異なのだ。 どうもこの人とはうまく噛み合わないなと感じたら、それは、互いの文化が異なるのだという認識にたって相手を見直してみると良い。 誤解というのは、人間関係のトラブルを招く大きな原因要素だが、それは、相手に対する認識不足、相手への理解不足から生まれることが多い。 認識不足は情報の不足によって生じる現象であるが、誤解というものは、多くの場合、当然解釈の違いから生まれる。 当然解釈が全く異なる異質の文化、つまり、何を当然とするかの物差し、価値の尺度を異にする文化が受け入れにくいのは無理のないことではある。しかし、だからこそ、人間関係、すなわち異なる文化を有する者どうしが交流する現場においては、相互理解のための努力が不可欠なのだ。私は、そのための早道は、良い、悪い、好き、嫌いの感情を抜きにして、まずは互いの文化土壌を知ろうとする努力なのだと思う。
![]()
人一人が有する文化土壌の中には、その人本来の持って生まれた気質に加え、その人が生まれ育ってきた歴史と、その人のキャラクターが育まれた文化土壌の背景がある。必ず、それぞれの人の思考や行動形態、そして価値観を生み出した歴史と奥深い文化土壌が存在するのだ。 ネーミング一つを考えても様々な理由があり、その理由は、その理由を生み出した文化土壌と無関係ではない。 その人がなぜ"そうなのか"という理由は必ずあるのだ。人一人をきちんと理解しようとするならば、現象だけに目を向けず、その現象が生まれた理由にもしっかり目を向けなければならないだろう。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會