
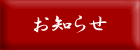 |
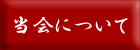 |
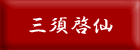 |
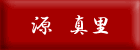 |
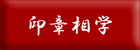 |
 |
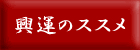 |
 |
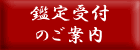 |
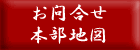 |

第23回 R・ニーバーの祈り 前編 ~開き直りのススメ~
![]()
「運命学って何なんだ、いったい何のためにあるんだ…。私は何をしているんだろう…」 そのころ私は一種のスランプ状態に陥って、自分がいる場所、自分が進むべき方向性が見えなくなりかけていた。
![]()
そもそも私は理不尽なことがきらいだ。確固たる信念のもとに、断固たる姿勢で、毅然として自分の道を進んで行きたい人のはずだった…。
![]()
なのに、そのときの私は、訳の分からないこと、訳の分からない状態にいいように翻弄されて右往左往していた。
もう完全な迷子状態!
まるで居候のような居ごごちが悪い日常…。
そんな状況や自分が無性に腹立たしくてイライラしていた。
![]()
『神よ、(それを)私が変えることのできないことに対しては、(私に)(それを)受け止める落ち着きを下さい』『(それを)私が変える事ができることに対しては、それをする勇気を下さい』『そして、(それが)私が変えることのできないことなのか、変える事ができることなのか、それを見分ける知恵を下さい』
![]()
R・ニーバーの祈りと呼ばれる、この台詞に出会ったとき、私は自分の目の前がパァーと開けていくのを感じた。私の中には一つの確信が芽生え、同時に自分の居場所も見つかった。その時を境に迷いが吹っ切れた今の私は、その芽を育てつつ"自分の居場所"の居心地を追及している。
![]()
私の信念は、そうとう大胆な仮説の上に打ち立てた理論に裏打ちされている。それは、 (良きにつけ悪しきにつけ)『この世には"運"というものが"存在する"』ということを大前提として組み立てられているのだが、その大前提の上で、私は『運』というものは、その作用が結果に影響を与える一つの要素であると考えている。そして、運命学のテーマは、"運というもの"および、"運とのつきあいかた"を考えることだと思う。このこと自体は、以前も今も変わってはいない。しかし、私の"運に向き合う姿勢"は確実に変わった。
![]()
金科玉条のごとく運命を論じ、ネガティブな運命観を押しつけて他人の人生を決め付ける、運命論者への反感も手伝って、当時の私は、運命は変えられると信じていた。運をチョイスすることで、結果をコントロールすることが可能なんだと思っていた。これは、私自身の (そうであって欲しいと願う)切なる希望でもあった。しかし、現実には、どうにもできないことが多すぎる…。私はここで迷子になっていた。
![]()
私の運命観が誤っているのか?
運命は"どうにもできないこと"なんだからあきらめろとでも言うのか?
いや、そんなはずはない!
でも…この"どうにもできないこと"に対処法なんてあるのか?
もしあるのならいったいどうすればいいんだ!…。
![]()
R・ニーバーの祈りは、そんな私に、正しい開き直り方を示唆してくれたのだった。
まず私は、『世の中には、"どうにもならないこと"が存在する』ということを認識した。そうしたら、"どうにもならないこと"を"どうにかしよう"とするより、"どうにかなること"を"どうにかする"ことを考える方がよほど効率的でかつ健康的ではないか!と、開き直ることができた。
![]()
そして、さらに考えを巡らすうちに、この世には、
①どうにもならないこと。
②どうにもできないこと。
③どうにかできること。
④どうにかなること。
そして、⑤どうにかできるかもしれないこと。
![]()
があると気が付いた。 そこで私は、まず、自分が運と向き合うときの基本姿勢を次のように決めてしまった。 ①"運"は、その作用の仕方で"宿命"と"運命"とにしっかり区別する。その上で、② "宿命"は自分の力では変えられない"条件"と考える。 ただし、それがどんな条件なのかをしっかり認識することは必要だ。それが、(どうにもならないことを)冷静に受け止めるということだ。 しかし、そこで、結果まで定まると考えるのは早合点というものだ。受け入れたのは条件だけ。その条件の下で、(それを前提にした)対処法を工夫する余地はまだ十分残っている。宿命に対して、(どうにもならないと思い込んで)ただ諦めてしまったのでは、宿命に流されてしまうだけだ。私としてはこれは避けたい。だから、諦めるのではなく、ちゃんと開き直ることにした。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會