
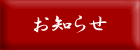 |
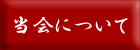 |
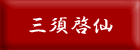 |
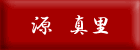 |
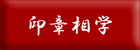 |
 |
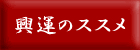 |
 |
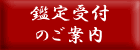 |
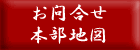 |

第26回 長編 指示待ち族と占いブーム 第一編
![]()
指示待ち族といわれる現代の若者の特徴は、自分から進んで創意工夫をしようとしない、そして判断するという能力が極めて低いということにあるのだと思います。独創性(オリジナリティー)を欠き、情緒性(エモウション)を欠き、個性(パーソナリティ)を欠く。しかし、独創性も情緒性も個性も必要としないことならば上手にこなせる存在といえます。
![]()
したがってテーマのみを与えて「さあやりなさい」といっても動けない。しかしマニュアルを与えてやり方を示せば、その通りにはできる。フィギアスケートにたとえればコンパルソリーはそつなくこなすが、フリーは苦手といったところでしょう。
![]()
では、なぜそうなってしまったのか…。答えは、そうなるようにしたからです。
![]()
躾と教育の過程で、自立した人間が行うべき『判断する』という行為のために必要な要素。判断の基準となるしっかりした(普遍的)物差しを与えなかった。なぜ良いのか、なぜ悪いのか、なぜそれが必要なのか。なぜそうなるのか…。なぜそれが必要なのかという『目的』を説明し、理解させるという手間と、さらにその目的を達成するための方法や手順とかを自分で考えさせる手間を省いて来たからです。結果に到達させるために必要な材料を与えることなく、結果を求め、試行錯誤の段階を踏んで次第に目的に近付いて行くという当たり前の、必要な手順を省いて来たからです。『教える』『導く』ではなく命令してそれに従わせる。定まった型から外れることを許さず、単一のルートのみ示して、それ以外の方法は認めない。これでは教育ではなく調教です。
![]()
彼等はいわば飼い馴らされた家畜かペット、もしくはサーカスの動物のようになっているのです。上手に芸をすれば愛され、褒められ、ご褒美ももらえます。しかし相手の望む芸を見せず勝手なふるまいをすれば、認めてもらえず、うとまれ、かまってもらえません。飼い主の気に入るようにして、お利口にさえしていれば危険も苦労もないのです。彼等がおとなしくお利口にしているのは、そうしなければ怒られるから。そしてお利口にしていれば褒められ、愛され、待遇も良いからです。しかし、怒られたくないから、褒められたいから「いい子」にしているうちにそれに慣れてしまった。そしてそれしかできなくなった。まさに『習い性となる』です。野生であったなら発揮できたであろう能力は眠ったまま放置され、可能性は狭められ、そして次第に退化していきます。
![]()
都合の良いように飼い馴らし、調教しておきながら、いきなり野に放って、野生の能力を要求してもそれは無理というものでしょう。褒められるための芸はできてもそれ以外のことは何をしたら良いか見当もつかないでしょう。与えられることに馴れ切った彼等は、与えられないことや、与えることには馴れていないのです。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會