
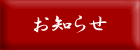 |
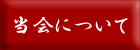 |
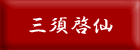 |
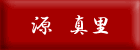 |
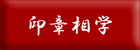 |
 |
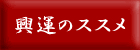 |
 |
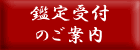 |
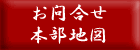 |

第20回 本当に印は無駄の権化なの? 後編
![]()
現在の日本社会では、原則として役所の(役所以外でも)書類には押印が必要とされている。(実は、ここにこそ問題の根があると私は思うのだが…)従って"書類の数だけ印が必要な場所がある"というのが現在の図式だ。そして、行政改革の諸課題の中で、役所の手続きの簡素化がテーマの一つとなって以来、押印の見直しが検討されてきた。
![]()
私が驚き、あきれるのは、「押印が必要とされている場所」の多さである。これは書類と、書類を必要とするセクション、そしてそれらの書類が必要だという人間の多さを示す。私は、このこと自体にこそ多くの無駄が含まれているのでは?と言いたい。要は、無駄な役所、無駄な役人、無駄な手続きが多すぎるのではないですか?といっているのである。
![]()
関所と通行手形に例えれば、現在、押印という行為は一種の通行手形の役割を担っている。(私は、印の使われかたの本道からみればこのこと自体が邪道なのではと思うのだが…)故に関所の数だけ通行手形が必要だった。それを今後は、関所を手形無しで通れるようにしようというのが今度の改正である。まあ、それはそれで良いとしても、本当は、関所そのものが必要かどうかの論議のほうがより大きな問題のはずではないだろうか。
![]()
現代の社会では、何かというと簡単、便利が優先されて、面倒、不便イコール罪悪であるかのような風潮がある。印が社会の合理化の敵とされている理由は、おおむね『面倒だから』と『無駄だから』ということのようだ。私は、総論としての、面倒なことを簡単にする、無駄を無くして合理化する、ということ自体に異論を唱えるつもりはない。しかし、面倒と簡単、無駄と合理的を分かつ"ものさし"に対してはけっこう言いたいことがある。
![]()
仮に、無駄イコール有罪として考えたとき、結果として生じる現象の無駄と、その現象を引き起こす原因の無駄とを比べて、どちらの罪がより重いかは明白だろう。原因がなくなれば当然、結果は無くなるのである。
![]()
私は無駄な印影、無駄な押印を無くすことには大大大賛成である。しかし、その前に、どうして無駄な印影が存在するのか、ということをよーく考えて欲しいのだ。そして、なにが"無駄"で、なにが"無駄でない"かという議論を慎重にして欲しい。私は、印章道に生きるものとして、邪道、外道な使われかたのために、印という存在、押印という行為自体が否定され不要であるという結論に短絡されてしまうのがなにより心配なのである。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會