
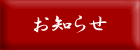 |
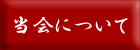 |
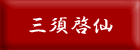 |
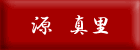 |
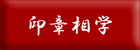 |
 |
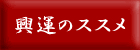 |
 |
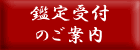 |
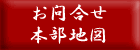 |

第27回 長編 指示待ち族と占いブーム 第二編
![]()
教育の理想は、(それぞれの人間が有する)素質の中に潜む可能性を伸ばし、広げて個性として育んで行くべきもののはずです。眠っている素質を目覚めさせ、磨きをかける手助けをしてやることなのではないでしょうか。そして何よりも、自分自身の中に、自他を正しく分析し、評価し、自己を律する判断の基準を持たせてあげる…セルフコントロールの機能をもたせて自立の条件を整えてあげることなのではないでしょうか。
![]()
しかし現実は、大人社会(親、先生、社会)は個々の素材たる子供の個性(資質、素質)を無視し、彼等の人間性(本来の姿)に目を向けることをせず、行動という外から見えるジャンルにのみ関心を払って、大人にとって都合の良い『良い子』のスタイルを定め、押し付けることに終始し、常に外部からの評価基準を押し付け、子供立ちの内面で進む「人格の形成」も無視して、画一的な型枠の中にはめ込んで、大人にとって不都合な部分や、余分な部分は切り捨て、矯正して、本来ならばもっと別の形になったかもしれない素材本来の可能性の目さえ摘み採って…。盆栽のような製品をせっせと製造してきたのではないでしょうか。
![]()
私の所に相談に来られる人々の中にも、わが子が理解できない、どうしたら良いか解らない…と頭を抱える親たちが大勢います。そんなとき私は、親と子供を「一人の人間が持つ個性」とそこから生じる可能性という観点にたって運命学的な側面からアプローチを試みます。その結果、素材が生かされていない、素材の扱い方がまずい、ということから発生するトラブルが実に多いと感じます。『本来あるべき姿をしていない』ことが生み出した様々な歪みが障害を生み出しているように思えるのです。
![]()
「子供の為に」という親の気持ちは痛いほどよく解ります。しかしとても残念なことですが、運命学的な立場から分析してみると、せっかくの気持ちが生きていない。結果として子供を親側の勝手な思い込みや、勝手な思い入れのために歪めてしまい、双方が苦しまずとも良いことで苦しみ、しなくとも良い苦労をしている状態で、努力が空回りしている不毛な状況を作り上げているという分析結果に到達することが多いのです。
![]()
指示待ち族、彼等にとって『判断の基準』となる価値の物差しは自己の内部にあるのではなく、常に外からあてられる物差しです。『怒られないこと』『褒められること』が成功であり、『怒られること』『褒められなかったこと』が失敗です。
![]()
彼等は判断されることに慣らされてしまったために、自分で判断することを放棄してしまったのです。そのかわりに自分にとって損か得か…という功利主義的な価値基準はしっかり備わっています。そして、自己本位の基準があるとすれば、外から評価されることのない部分、自己の内側の世界のこと。楽しい、気持ちいい、楽、とかいった利己的なミーイズムの物差ししかありません。それが唯一彼等に許された『自分で決めて良いこと』だったからです。しかし、そこは未発育のまま放置されていたため極めて幼稚で我が儘です。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會