
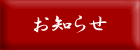 |
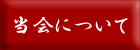 |
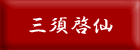 |
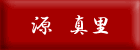 |
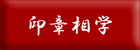 |
 |
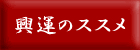 |
 |
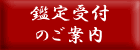 |
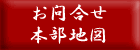 |

第31回 運命学が有する先見性と洞察力 前編
![]()
阪神大震災の後で、数人の占術家が、自分は震災を予言し的中させた云々のコメントが週刊誌で取り沙汰されていたが、そのとき、予言の定義について父と話し合ったことを踏まえ、私の"占い"というものに対する考え方と認識を語りたいと思う。
![]()
例えば地震の予知について考えてみる。
いつ(日時)
どこで(場所)
どれぐらい(規模)
![]()
父(三須啓仙)との議論の中では、"予言"の"的中"というには、この3点についてどの程度の精度が必要か…ということがテーマとなった。現代の、いわゆる科学のジャンルにおいては、(どこで)(どのぐらい)という事に関しては、(なぜ)という理由も含めてかなりの精度で予測ができるという。これらは、長年の研究の成果として様々な角度からの情報が蓄積され、その情報を分析した結果、そこに一定の法則性を見出だして傾向がつかめたからだろう。
![]()
つまり、
![]()
■情報の蓄積
■分析
■帰納
■法則性の発見(仮説の構築)
■演繹
■予測
![]()
という思考の手順が確率するからだ。 しかし、テーマが(いつ)という問題になると、実用的といえる範囲の精度で予測することはできないのだそうだ。
![]()
地質学のジャンルで流れる時間のスパンは、人間の生活感覚の中で流れる時間感覚に比べて極めて長い。例えば5年、10年という単位は、地質学的に見れば十分に高い精度であろうと思われるが、人間の生活における(実用的と思われる範疇の)時間感覚からは、とても長い時間であり、これでは、私達が期待する意味での"予言"といえる精度の情報は得られない。
![]()
では、占いのジャンルではどうだろうか…。
![]()
この場合も、予測のシステムは原則としていわゆる科学のジャンルと変りはしない。占いにおける予測は『ある現象は、運命学的に見て、ある条件が揃った時に生じる』というセオリーに則って行う。従って、ここでも当然データの集積が必要だ。 以上を踏まえて私達が達した結論は、予測に必要なデータを集積するために、例えば『地震の予知』ということにテーマを絞って次のようなステップを踏んで研究すれば、ある程度可能かもしれない…ということだった。
![]()
ステップ1 科学のジャンルにおけるこれまでの研究の成果を踏まえ専門の知識やデータを活用し、まず地震が起きそうな場所や時期を候補として絞り込む。
![]()
ステップ2 その上で、地震に対する運命学的見地からの時間的、場所的、内容的な定義を設定するための研究を進め、必然の要素となる条件を探して事象と重ね合わせる。
![]()
ステップ2における留意点として、まず、運命学のジャンルの中からどの方法をチョイスするかを考えなくてはならない。予知の目的に適した占法を選ばねばならぬのだ。
![]()
人が起こす現象ではないのだから、姓名学や人相や手相のジャンルでは地震の予測は出来ない。…これは"時の作用"なのか、"方位の作用"なのか、方位の作用とすれば何を基準としてどこを中心に考えたら良いのか…。 運命学的な見地からの"原因"となる要素を絞りこんで考えていくことから始め、言わば地震予知専用の判断基準・物差しを設定しなければならない。
![]()
例えば気学で見るとしたら、易で見る時は、アストロロジーなら…。試行錯誤を重ねていくことになるだろう。
| 目次へ戻る |
当サイトに掲載の記事・写真・イラスト等の転載を禁じます。
Copyright 2003 聖德會